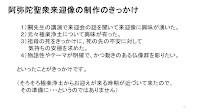昨日は神奈川県伊勢原市の日向薬師宝城坊と雨降山大山寺
(あふりさんおおやまでら)を参詣した。お寺の縁起では、
関東屈指の古刹と言える。参加者は健脚の男女11名。
今年5月、金沢文庫で日向薬師 秘仏鉈彫本尊開帳の特別展を
観覧した。この時に、日向薬師の参拝を計画していた。
近辺の大山寺がご本尊のくろがね不動尊や秘仏の諸尊像を
ご開帳されるとの情報を得て、今月実現することとなった。
伊勢原駅からバスで終点「日向薬師」まで行く。
そこから徒歩で山道を上って行く。15分程歩くと、
山門の仁王像が眼前に現れる。
山門を抜け、更に鬱蒼とした林の中を進む。
バスの終点から坂道を登る 階段の先に山門
吽形 阿形
山門を過ぎて更に上る
本堂は改修中であり、シートで覆われおり、参拝できない。
向かった先は宝物館。ここに、重文クラスの仏像が数多く
安置されている。
日向薬師の縁起によると開基は行基となっている。
開基の行基にも、文化財の多さにも驚く。
縁起と文化財一覧 宝物館仏像の安置図
宝物館には丈六の薬師如来像(三尊像)と阿弥陀如来像が
館内の東西にどっしりと鎮座している。いずれも鎌倉時代の作で重文。
慶派による造像の可能性が指摘されている見事な像だ。
恐らく、いずれかの堂塔に、ご本尊として祀られていた像と推察される。
この2体を拝観できただけでも満足する。
館内正面の厨子を囲むように四天王や十二神将が所狭しと
並んでいる。四天王は、奈良・興福寺南円堂四天王像に近い
雰囲気が見られる。
こちらも間違いなく、慶派仏師のなかでもかなり優秀な人の作
ではないかと言われている。
また、十二神将は大小二組の像が交互になって立っている。
小さい方の像は平安時代の作とのことであり、中にはVサイン(刀印)を
出しているような像もある。
また、今まで見たこともないポーズを取る千手観音は愛嬌がある。
薬師三尊像 阿弥陀如来坐像
(金沢文庫 特別展の図録から)
厨子の周りの四天王像が見事 拝観を終え、宝物館を後にする
日向薬師での拝観を終え、元来た道を逆コースで戻った。
伊勢原駅前で昼食を済ませ、午後からは大山寺へ向かう。
午前中とは別ルートのバスに乗り、徒歩、ケーブルカー、
と乗り継ぎしながら大山寺に辿り着く。
午前中に比べ、少しハードな行程。
駅バス停から見える鳥居 バス停を降りケーブルカー目指して歩く
ケーブルカーで大山寺へ向かう
大山寺に到着して、早速、外陣から参拝する。
その後、拝観料を納め、内陣に入り、数々の
仏像を拝観して回った。
大山寺の開山は東大寺の初代別当良弁(ろうべん)
僧正とのことだ。
大山寺に到着 お寺の歴史
内陣左手には不動明王を中心にして周りを4明王が囲む
五大明王像が目に入って来た。造像もしっかりしている。
中央にはご本尊のお前立となる不動三尊像が並び
不動明王のお姿が見えないくらい大きな倶利伽羅龍が
刀に巻き付いていた。
更にこのお前立両脇には、向かって左右に分かれ
金剛界、胎蔵界の大日如来が鎮座している。
また開山良弁僧正と、弘法大師空海も両脇に祀られていた。
お前立の奥へ進むと、ガラス張りとなった中に、ご本尊の
くろがね不動明王三尊像が安置されていた。
鎌倉期、重文の見事な像だ。玉眼は後補か、異様に光っていた。
仏像と言えば、木造、銅造、乾漆造、塑造などが一般的だ。
鉄造の仏像はあまり、聞いたことがない。
五大明王像 ご本尊 鉄造 不動明王三尊像
(ネットでの画像)
ご本尊の真ん前(お前立と背中合わせの場所)に、
秘仏三面大黒天が安置されている。
この作者が高村光雲とのこと。
高村光雲は今年ご開帳となった高野山金堂ご本尊の作者でもある。
中央が大黒天、左右に、毘沙門天、弁財天を配置したご利益の
多そうな像と言える。
三面大黒天は豊臣秀吉の念じ仏として有名。
秀吉はこの仏像を戦場にまで携行したようだ。
また、秘仏の愛染明王や如意輪観音も拝観できた。
これだけ沢山の仏像と一時に接し、大変得をしたように感じられた。
最後に、記念撮影をして、今回の見仏会を締めくくった。
本堂を背に記念撮影
日向薬師、大山寺の創建に関わる人物として、行基(668~749)、
良弁(689~774)、空海(774~835)が登場する。
日向薬師の宝物館にも、薬師三尊像の脇に行基(向かって右)と
空海(左)が祀られていた。
生存年を見ると行基、良弁は同時代を生きた人であり、
共に聖武天皇を支え、東大寺創建と大仏開眼に多大な
功績を残した。
良弁が亡くなった年に空海が生まれたことも不思議な縁を
感じる。
旧仏教である南都六宗に対して、新仏教として台頭したのが
最澄の天台宗と空海の真言宗。
日向薬師も大山寺も東大寺(華厳宗)と言う南都のお坊さんが
創建した寺院。
空海は旧仏教創建の寺院も引き継いでしまう融通無碍な、
懐の深いところがあるように思える。
空海は敵対しないで、すべて吸収してしまう。
この2寺院の創建縁起を見ても、感じた。
今回も、本当に楽しい、充実した一日となった。
ご参加の皆さん、共に過ごせた貴重なお時間
有難うございました。